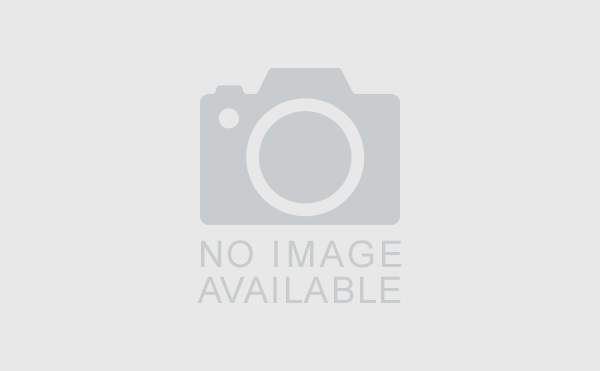働くことの意味を再確認~『仕事漂流』
いつも投資についてのテーマをメインに書いているので、たまには休憩がてら、まったく関係のない書籍の書評ブログ的なこともしてみたいなと思います。
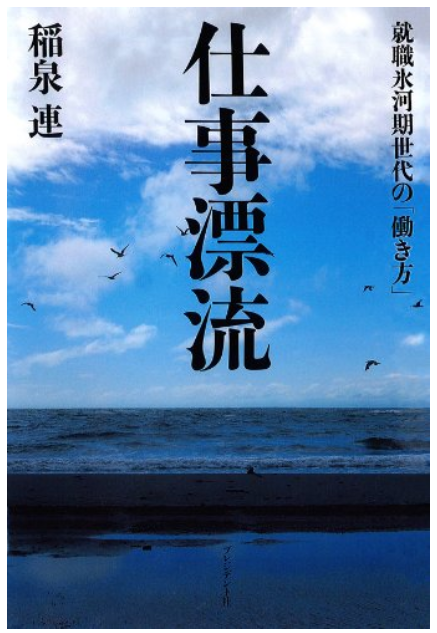
タイトル:仕事漂流 就職氷河期世代の「働き方」
特にベストセラーではありませんが、社会人になって働くことが辛いと思ったときによく読んでいました。
就職氷河期世代の8人のノンフィクション
本書では、就職氷河期世代と言われる年代の方8人の、働き方、転職、生き方を綴ったルポルタージュです。
特に、有名大学卒の高学歴でも就職が難しかった人たちについて書かれています。希望した就職ができずに苦悩した人、第一志望の企業に入れたけれど、働き方に納得がいかず転職を決意した人、成長したい為に海外留学した人等、様々です。就職についてだけでなく、その人の生い立ちから、働くことに対する考え方に至るまで、彼らの人生を体感できるような内容になっていると感じました。
特に印象に残っている2人について、私の感想を書きたいと思います。
1.”私にできることって何だろう”
第一志望の出版会社への就職が叶わず、菓子メーカーの職についた女性の話です。
希望通りの就職ができなかったけれど、最初に入社した場所で、働くことへのやりがいを見出そうと頑張るのですが、売り場で一緒に働く上司の言動に耐えれらず、体調を崩して休職。
ここまで読んだとき、あぁ、やっぱりどこにでもいるよな。人を壊す人、って思いました。でも、私も少し似たような転職をしていたので、共感する部分は大いにありました。一言でいうと、逃げてもいいんだっていうことですかね。
自分がもっている自分の生き方の指標の一つとして、”他人は変えられないけど、自分自身や自分の環境を変えることはできる” です。
ぶっちゃけ、私も前職が辛くて会社を辞めました。確かに給料は決して安くなく、福利厚生も充実した場所でしたが、自分の仕事を上司に否定され続ける毎日に日々自信を失っていました。
精神的に参っている時に、落ち着いて振り返ってみたんですよね。今、自分は幸せなのかな?、と。自分が幸せを感じる時ってどんな時なんだろう?、と。
一概に幸せは、もらえる高い給料だけでは満たされない、と考えました。私みたいな普段お金をあまり使わない人間にとっては、金銭的報酬で得られる幸福感が比較的低いのかもしれません。
彼女は、菓子メーカーの販売職 → 食品会社の総務 経理部門 という転職をします。自分の環境を大きく変えることで、前向きに、そして自分の成長を感じることができるようになったという点は、共感きる部分が多々ありました。
彼女と重なる部分は、自分にできることを見つけ、その場所に行き、人から認めてもらうことが、自分にとっての一番の幸せなのかなと思ったところですかね。周りから認めてもらうことを社会的報酬と呼びますが、幸福感に対するその効果は非常に大きいと思います。
1.”常に不安だから、走り続ける”
2人目は、コンサルタント職を転々としている男性の話です。
一言でいうと、”ストイック”。彼の職種は、企業買収や合併を扱うコンサルタント職なので、日々様々な情報を武器にし、それを使いこなすスキルが求められる場所です。企業に属する人達の生活をも左右する、とても大変な仕事だと感じました。
印象的なのは、今日わからなかったことがあれば、明日その専門の人くらいのレベルになっている必要がある、という彼のスタンス。
常日頃から向上心をもって、貪欲に、己を磨き続ける彼の姿勢は圧巻で、私の理想でもあります。経済新聞を購読し、毎朝自分を”アップデート”する感覚を得て、自己研鑽をずっと続ける。うーん、実際できていない(笑)。
彼の職場に、ある新人社員の女性の話が出てきます。彼女は、自分にできることが何なのかずっとわからず、不安そうな顔で日々過ごしていたそうです。
その職場は、良くも悪くも個人主義でどこまでもドライ。チーム意識は低く、それぞれ個人が自分で努力して地位を気付いていた人が多い場所だと言っています。
それは、まさに私の転職前の環境と多々重なるところがあると感じました。なにくそ根性で、その環境をエネルギーに変えられる人は、そこでのし上がれるかもしれない。けれども、”やさしい人”は、その環境に合わない場合もある。周りに相談しづらい雰囲気がある点も似ていました。
相談するときにも、わかりません、はご法度。人に相談する時は ”私はこう思うのですが…”と意見を言う。自分で考える癖をつける。ビジネスパーソンとして、これは非常に大事ですよね。
彼のルポは、非常に自分のモチベーションになります。しかし、私の理想であって、私は彼と同じにはなれない。逃げるということではなく、そこは自分でしっかり認めてあげることが重要だと思います。
この書籍、初版が2010年と若干古いのですが、働き方についての読み物としては、非常に優れていると個人的には思います。なんというか、あぁ、こんな考え方もあるんだなぁ、と救われる気持ちになるんですよね。
という意味で、個人的におススメの1冊です。